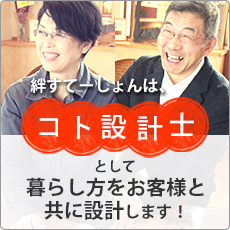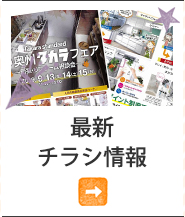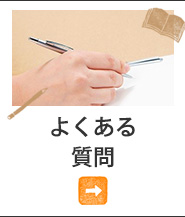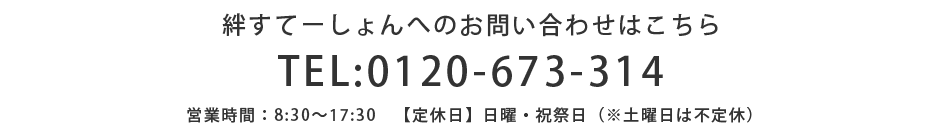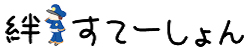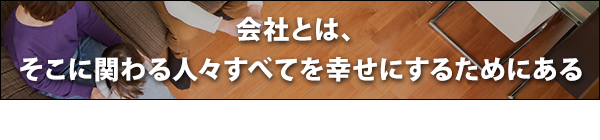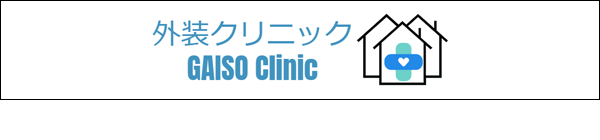設える
- 投稿日:2022年 11月24日
- テーマ:住まい

「設える(しつらえる)」という言葉を耳にする機会がなくなりましたね。
この言葉は、平安時代の「しつらい」という名詞に語源があるようです。
「しつらい」とは「室内などに飾りなどを調度すること」を意味する名詞でした。
以降、この「しつらい」という名詞が「しつらい」→「室礼」→「設い」と
時代と共に漢字が充てられていったようです。
この「室礼(しつらい)」という言葉は、室町町時代に
武家屋敷の様式である「書院造」が誕生し、
床の間が出現し使われるようになりました。
床の間はお客様を迎える部屋になります。
古い我が家にもありましたが、実際には物置になっておりました。
現代では茶の湯をはじめ、旅館や料亭の床の間に
季節の掛物と花をいけることで、
お客様への「おもてなし」として継承されています。
現代の住まいには床の間がなくなっています。
しかし日本人として客人をもてなす気持ちは残して置きたいものですね。
そこで、玄関・リビング・ダイニングの一角に、季節の
小物を置くことだけでも楽しいものです。
右の写真は、わが家の玄関にあるニッチの壁に
息子が小学生の時に書いた絵を飾ったものです。
このように気取らずに「しつらえる」だけで
心が温かくなるものです。
石川シュウジ
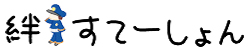

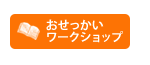


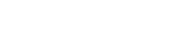

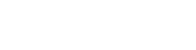
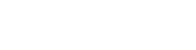
 0120-673-314
0120-673-314 電話で見積り・相談
電話で見積り・相談