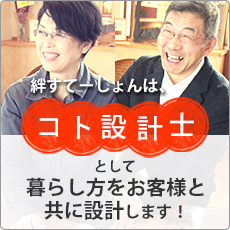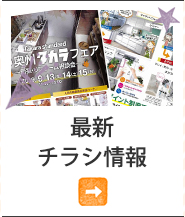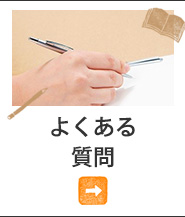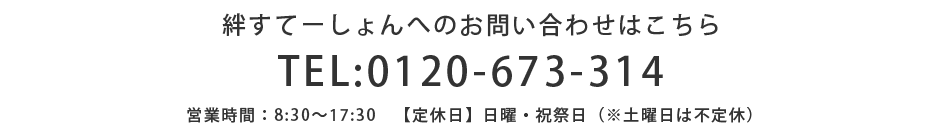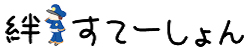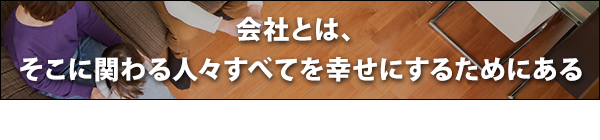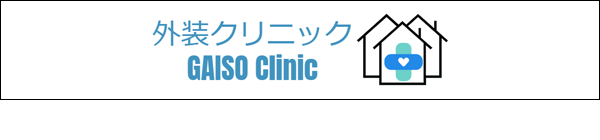「在宅介護」と住宅リフォーム
- 投稿日:2022年 2月28日
- テーマ:アンチエイジング・ハウス / 住まい / 理念
私たちコンパスウォーク北上鬼柳の利用者様の中には、
以前弊社でリフォーム工事をされているOBのお客様もいらしゃいます。
有難いことですね。
先日相談員である妻・利佳子が訪問した利用者様もOBのお客様でした。
そこで介護をしているご家族様から相談員が言われてきたことを、帰社するなり私に報告してきます。
ご家族様: 「またご縁あってコンパスさんにお世話になっておりますが、
何より以前にトイレの改修工事をやっていて本当に良かったと思います。」
相談員 : 「それは嬉しいお言葉です。」
ご家族様: 「ドアから引き戸に直したのがとても良く、親も一人で利用することができます。
又、床と壁にホーローパネルを貼ったので、とても掃除が簡単で楽ちんです!」
相談員 : 「介護してみて初めて使い勝手の良さが分かる場合もありますよね。
時間が限られる中で掃除が楽なのが一番ですね。社長の石川も喜ぶと思いますよ!」
実際に介護されているご家族様から、トイレを利用しての感想をいただくとはなんと嬉しいものでしょうか!
やはり費用が掛かっても、使い勝手の良い製品や間取りをお勧めして良かったと思います。
実は介護リフォームは、実際に介護が必要になるとできないものなのです。
仮設のトイレを設置しても、段差があったり、夜間外に出て用を足すことが難しいからです。
何よりも介護がいつまで続くのかが不安になり、お金があっても介護保険を使う住宅改修では、
上限を目途にしてする間に合わせの改修が多く見受けられます。とても残念なことです。
介護リフォームという狭い見方ではなく、子育てから介護までが楽にできるユニバーサルデザインを取り入れることは、家族の誰もが使いやすいということになります。
特に排泄は、自分でできることがその人の誇りを護ることに直結するのです。
石川シュウジ
「ヤングケアラー」少なくとも34人 県が初めて調査
2020年度、岩手県はやっと重い腰を上げて県内33市町村にある、
民生児童委員や各役所の福祉課職員などで構成する要保護児童対策地域協議会を通じて
「ヤングケアラー」の調査を実施しました。
初の調査結果を公表し、昨年6~7月の段階で、県内に少なくとも34人いるとみられるとしています。
年代別では、小学6年生と中学2、3年生が最多で、各学年5人。
多子世帯では、きょうだいの間で世話をしあうケースがあり、
小学校低学年の児童がさらに年齢が低い子どもの世話をしている事例もありました。
そのため、県内のヤングケアラーは小学1年生から高校生まで、
幅広い年齢層にわたっているといいます。
実際に世話をする対象(重複回答あり)は、幼いきょうだいが23件と最も多く、次に親が15件でした。
県の子ども子育て支援室によると、ヤングケアラーの場合、
自分たちが支援を必要とする対象者だという自覚がなく、
周囲に助けを求めない傾向にあるといいます。
高齢者福祉と比べ、公共サービスが充実していない側面もあります。
そのため、同室の田内慎也課長は「潜在化しやすい」とコメントしています。
(石川:自分たちが仕事をしていないことを認めています)
今回の調査で分かった34人のうち、29人が虐待やネグレクト(育児放棄)を受けている児童で、
もともと行政などによる保護の対象者でした。
(石川:これでは調べたといえません)
このことから私は、この数字は氷山の一角だと考えます。
私もかつて児童民生委員を一期だけ務めた経験がありますが、
地元にいても家庭内の様子をうかがい知ることは難しいことなのです。
個人情報の壁、ご近所付き合いの希薄化など、一歩踏み込めないのが現状なのです。
行政は教育福祉問題について、児童民生委員に対応を求めますが、
市町村の仕事の下請け先ではありません。
厚生労働大臣から委嘱されている立場ですが、権限が限られております。
児童民生委員には、もっと権限と報酬を与えるべきです。
ボランティアが無償の奉仕だと考えているのは、
世界において日本だけなのです。(脱線しました)
石川シュウジ
ヤングケアラーって何?
- 投稿日:2022年 2月26日
- テーマ:アンチエイジング・ハウス / 住まい / 理念

子どもが家事や家族の世話をすることは、ごく普通のことだと思われるかもしれません。
お手伝いすることは、人間形成にとって大切なことだと私も思います。
しかし、ヤングケアラーは、年齢等に見合わない重い責任や負担を負うことで、
本当なら享受できたはずの、勉強に励む時間、部活に打ち込む時間、
将来に思いを巡らせる時間、友人との他愛ない時間など、
「子どもとしての時間」と引き換えに、家事や家族の世話をしていることがあるのです。
核家族化が進み近所との付き合いも減っているのも一因になります。
さて最近マスコミでも取り上げられるこの「ヤングケアラー」とは、
本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを
日常的に行っている子どものことを言います。
周囲の私たち大人が気付き、声をかけ、手を差し伸べることで、
ヤングケアラーが「自分は一人じゃない」「誰かに頼ってもいいんだ」と思える、
「子どもが子どもでいられる街」を、みんなでつくっていきませんか!(厚生労働省)
こういうのは他人事で簡単なことです。
しかしその実態さえも把握されていないのが問題なのです。
石川シュウジ
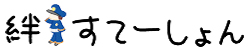

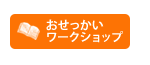


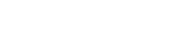

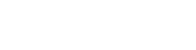
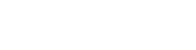
 0120-673-314
0120-673-314 電話で見積り・相談
電話で見積り・相談